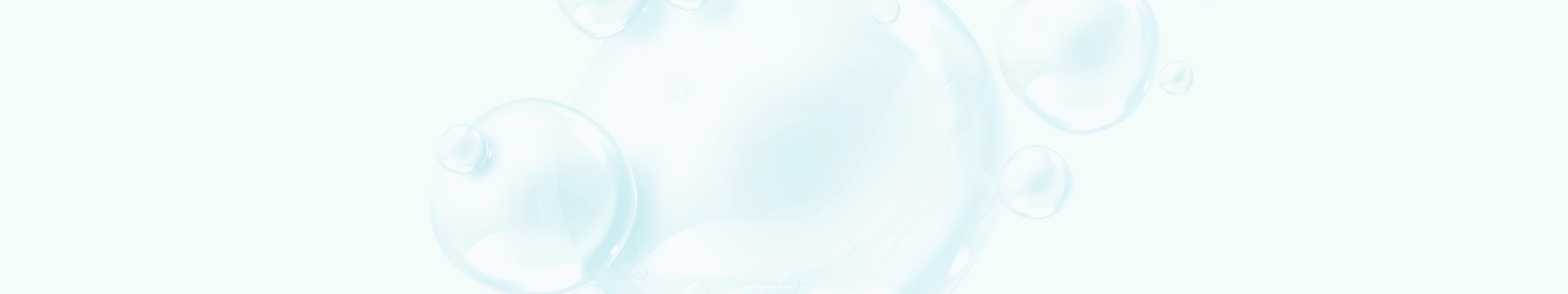病院経営のリアルを語る:日本全国の病院が赤字率61%という現実
星剛史 × 清水大輔|対談シリーズ「Healthcare Heroes」
物価高騰、人件費の上昇、人口減少――
かつて経験したことのないスピードで、医療機関を取り巻く環境が変化しています。経営努力をしてもなお赤字に陥る病院が続出し、全国の約6割の病院が赤字という異常事態が続いています。
こうした危機的状況に、私たちはどう向き合うべきなのでしょうか。
そのヒントを探るべく、病院経営の現場を熟知する二人の対談を収録しました。
本記事では、YouTubeにて公開中の対談
「病院61%赤字という現実とこれからの経営戦略」
の内容をもとに、テーマごとにわかりやすくまとめています。
対談に登場するのは、長年にわたり公立・民間病院の経営支援に携わってきた弊社代表コンサルタントの星剛史と、元医療経営専門誌の編集長であり、現在は医療ジャーナリストとして幅広く活動する清水大輔氏。
現場のリアルと政策の動きを深く捉えたこの対話が、貴院の経営改善や将来構想の一助になれば幸いです。
病院の赤字率61%という現実
今、日本全国の病院の61%が赤字という衝撃的な数字が報告されています。
これは単なる一時的な経営不振ではなく、長期的かつ構造的な問題です。都市部だけでなく、地方の中小規模病院にも影響が及んでおり、地域医療の崩壊リスクが現実味を帯びています。
NHKの特集番組でも「都市部でも病院閉鎖が相次ぐ」など、これまで安全圏と思われていた地域でも事態は深刻です。
医療の質を維持しながら、経営を成り立たせるという基本的な使命すら危ぶまれている状況に、多くの関係者が頭を抱えています。
清水氏は「これほど病院経営が深刻になったのは過去に例がない」と述べ、もはや個々の努力では解決できない問題であることを強調。
星も「従来の経営改善手法では限界がある。これまでの延長線では生き残れない」と指摘し、経営戦略そのものの転換を迫られていると語っています。
経営努力しても赤字…今までと何が違う?
以前は「非効率な経営」「人手不足」「収益管理の甘さ」などが病院赤字の主な原因とされてきました。
しかし、今赤字に転落している病院の多くは、こうした課題にすでに取り組み、経営改善を果たしてきた病院です。
それでも赤字、というのが今の現実です。
清水氏は、「ここ数年で何が変わったかというと、診療報酬が現実のコスト上昇に全く追いついていない」と指摘します。
例えば、委託費(給食、清掃、警備、医療廃棄物処理など)は大きく上昇。医薬品や診療材料も価格が高騰しており、特に水道光熱費の値上がりは無視できない規模です。
さらに、職員の処遇改善の必要性が高まる中で、人件費の上昇も避けられないテーマとなっています。
しかし、その一方で診療報酬は2年に一度の改定に過ぎず、しかも微増にとどまるため、実質的にはコストアップに追いついていません。
星は「経営者としてのやりがいすら失われかねない構造になっている」と語り、経営における達成感すら感じにくい時代に入ったと分析します。
急性期病院の苦境と人件費の増加
急性期病院は、高度な医療を短期間で提供することを目的としており、その分人件費や設備投資が多く必要です。
これまでも経営的には厳しい環境でしたが、近年では人件費比率が60%を超える病院も珍しくなくなりました。
これは以前の「50%を切るのが理想」とされた時代と比較しても、大きな変化です。
急性期では、医師や看護師に加え、臨床工学技士や薬剤師、リハビリスタッフなど多様な専門職が求められ、加えて夜勤・当直体制など人的リソースの負荷が非常に高いです。
清水氏は「異業種での賃上げが進み、医療職が相対的に割に合わない職業になりつつある」と警鐘を鳴らします。
星は、「給食や清掃、委託先企業でも人件費が高騰しており、医療現場以外でもコスト増が止まらない。しかもこれらは診療報酬ではカバーされない」と具体的な例を挙げ、経営上の負担感の増大を説明します。
一方で、看護職やコメディカルの待遇改善は、医療安全や離職防止にもつながるため簡単には削れない。
つまり「削れないコストが増えている」というのが急性期病院の苦境を象徴しています。
医師のキャリア多様化と人材偏在
医師のキャリアは今、大きく変化しています。
かつては「大学→医局→関連病院→開業」という一本道のキャリアモデルが主流でした。
しかし今では、美容医療、ベンチャー起業、海外留学、フリーランス、さらにはSNS発信を軸にした活動まで、選択肢が爆発的に広がっています。
星は「SNSやYouTubeで多様な生き方が可視化されたことで、勤務医のままでいいのかという疑問を持つ若手が増えている」と語ります。
清水氏も「専門医資格を取らず、20代で開業する医師も増えてきた。従来のキャリアパスにとらわれない医師が急増している」と述べ、医師配置の計画そのものが難しくなっているといいます。
この結果、都市部には医師が集中する一方で、地方や僻地には医師が行きたがらない。
国も医学部の地域枠制度や診療報酬による地方優遇などを導入していますが、強制力が弱いため大きな効果は得られていません。
星は、「医師の人権を尊重しつつも、どうやって地方医療を守るか。そのバランスを見直す時期に来ている」とまとめています。
地方病院の医師確保の難しさ
地域に根ざした病院ほど、医師の確保は年々厳しくなっています。
都市部の病院では応募があっても、地方や中山間地域にある病院では、募集しても医師が集まらないというケースが続出しています。
清水氏は「地域偏在の解消のため、様々な政策が導入されてきたが、成果は限定的。地域枠で入学した医学生が、卒業後も本当にその地域に残って働き続けるかは別問題」と指摘します。
星は実際の現場感覚として、「愛知県でも内科医の確保が難しく、派遣を打診しても断られるケースが増えている。特に総合内科のような病棟全体を支える存在は、本当に貴重になってきている」と強調します。
また、地方病院では「呼吸器内科」「糖尿病内科」など専門分化された医師が少ないため、1人の内科医が非常に幅広い領域をカバーすることになります。
これは業務負担としても大きく、結果として離職につながる悪循環を生んでいます。
国の制度としても、診療報酬で地方優遇する形は取られているものの、「医師が働きたい」と思える環境整備がなければ根本的な解決には至らないのが現実です。
医療費削減政策と病床削減の問題点
近年、国の財政悪化を背景に、「医療費の適正化」という名のもと、医療費削減政策が打ち出されています。
その象徴が「病床削減」です。
政府は将来的に11万床を削減するという目標を掲げ、削減1床あたり約400万円の補助金を交付する事業を展開しています。
清水氏は、「すでに多くの病院がこの補助金を求めて申請しているが、そのほとんどが“元々埋まっていない病床”を対象にしている。つまり“使っていない病床をなくすだけ”で、本来の医療費削減にはつながっていない」と語ります。
星も、「病床を減らしても、その分医療人材が余るわけではない。看護師やコメディカルは別の医療機関に移るだけで、結果的に医療費の構造自体は変わらない」と指摘します。
さらに問題なのは、「病床を減らすこと」と「医療の質を高めること」が必ずしもリンクしていない点です。
例えば、外科医2名ずつしかいない2つの病院を統合し、外科医4名の体制とすることで、安全で高度な医療が実現します。
しかし、これは病床削減ではなく「病院統合」であり、政策の方向性とのずれが生じています。
高齢者救急と地域包括医療病棟の使いづらさ
高齢者の救急医療のニーズは年々増加しています。
誤嚥性肺炎、脱水、軽度の脳梗塞、尿路感染症など、命に関わるほどではないが即時対応が求められる症例が急増しています。
これに対応するために新設されたのが「地域包括医療病棟」です。
急性期の患者を直接受け入れ、短期間での回復を目指すことを目的とした制度ですが、実際には普及が進んでいません。
星はその理由を「制度設計が現場感覚と合っていない」点にあると指摘します。
例えば、21日以内の在院日数制限、必ずしも高くない診療報酬、内科医の不足などが障壁になっており、「誰がこの患者を診るのか」という根本的な課題が解決されていないのです。
清水氏も「制度の理念は正しいが、現場で実装しにくい。今の制度のままでは、普及が頭打ちになる」と述べ、次回診療報酬改定での見直しが急務であると語ります。
診療科の統廃合とコスト最適化
病院の診療科を増やせば増やすほど、そこにかかるコストも比例して増えていきます。
医師、看護師、医療機器、スペースの確保…すべてが重荷となり、特に地方病院では、実際にその診療科を必要とする患者が年々減っているという状況があります。
星は「特定の診療科の患者がほとんど来ないのに、医師と設備を置き続けるのは経営的に持たない。決断すべき時期が来ている」と語ります。
清水氏も、「新しいことを始めるより、既存のものをやめる方が圧倒的に難しい。職員や地域の理解も必要だが、第三者であるコンサルが入ることで、意思決定が進みやすくなる」と述べます。
診療科の絞り込みは、「住民の医療アクセスを損なうのでは?」という懸念もありますが、実際には「より高度な医療を提供できる体制を再構築する」ことが目的です。
遠方への通院が必要になるケースもあるかもしれませんが、総合的な医療の質と持続可能性を考えれば、避けて通れない議論といえるでしょう。
病院の在宅医療参入と地域連携の課題
少子高齢化が進む中で、「入院より在宅」という医療の流れが加速しています。
患者本人の希望や家族の介護負担、入院医療費の高騰といった背景からも、在宅医療の重要性は増しています。
しかし、病院と開業医の機能分化が進んでいる現在、病院が在宅医療に参入することには一定の摩擦もあります。
星は、「病院が在宅医療を担うことは、入院との連携を強化する意味で非常に意義がある。必要なときに迅速に入院につなげ、回復したら在宅へ戻す。この循環を病院が中心となって担えるのは大きい」と述べます。
一方で清水氏は、「病院が在宅医療に踏み込みすぎると、地域の開業医との役割が重複する。
信頼関係や分業バランスを崩さないための配慮が不可欠」と指摘。
地域全体で医療資源をどう使い、どう連携するかの仕組みづくりが鍵になります。
加えて、在宅医療の展開には訪問看護師や多職種の連携体制も欠かせません。
単に「やろう」と決めても、すぐに実行できるほど現場には余裕がなく、人材・制度・財政の三重の壁を越える必要があります。
病床削減では医療費削減に繋がらない理由
国の医療費削減政策の一環として進められている「病床削減」は、果たして本当に効果的なのでしょうか。
清水氏は「医療費の約半分は人件費。その構造が変わらない限り、病床数を減らしたところで医療費全体はさほど変わらない」と述べます。
星も「空床が多い病院がベッドを減らしただけでは、医療費は削減されない。それどころか、医療の質が落ちたり、患者が遠方の病院へ通わざるを得なくなったりと、住民への悪影響が出かねない」と懸念を示します。
さらに、病床を減らすということは、多くの場合、人員削減や病院設備の縮小を意味します。
これは地域医療提供体制の“後退”にもつながりかねません。
真に必要なのは、患者数や疾患構成、地域特性を踏まえた「適正配置」であり、単純な“数合わせ”ではないのです。
病院統合と医療のグループ化の必要性
病院の数を減らすことには、単なる「削減」ではなく「統合」という別の可能性があります。
特に外科医や専門医が不足する中小病院では、統合による医療の安全性と効率性の向上が期待できます。
星は、「外科医2人の病院が2つあるなら、統合して4人の外科医がいる1つの病院にすべき。手術の質も安全性も格段に上がる」と具体例を挙げます。
清水氏は、「医療グループ化により、医師や職員の共有、診療機能の再配置、バックオフィス業務の一元化など、さまざまなスケールメリットが期待できる。連携より、グループ統合のほうが現実的で持続可能な形」と指摘します。
また、グループ化によって患者情報の共有もスムーズになり、複数の病院で統一された医療が提供可能に。
これは患者の安心感にもつながり、地域全体の医療の質を底上げする効果が見込まれます。
医師の共有・情報連携が進む未来
医師不足が深刻化する中、「医師をどう配置するか」ではなく、「どう共有するか」という視点が求められています。
清水氏は、夜間当直医を複数の病院でシェアする新しい取り組みに注目します。
「オンラインを活用し、複数の病院を1人の医師が遠隔でカバーする。これは“集約”の先駆け」と述べ、情報連携の仕組みを強化する必要性を訴えます。
星も、「カルテ情報が複数の病院間で共有できれば、患者がどこを受診しても自分の情報が参照できる。病院のグループ化が進めば、こうした体制整備も現実味を帯びてくる」と語ります。
このような医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展は、単なる効率化ではなく、医療の質と安全性を高める手段でもあります。
特に慢性期や高齢者医療においては、切れ目のない情報連携が患者の安心とQOLを支える基盤となるのです。
病院ができる新たなサービスと信頼の活用
医療機関が持つ最大の資産は「信頼」です。
この信頼を活かした新たなサービス展開が、今後の病院経営のカギとなります。
清水氏は、「保険診療だけに頼るのではなく、信頼関係を活用して自由診療や生活支援サービスなどに広げていくべき」と提案します。
例えば、医師が監修した健康食品や栄養指導、禁煙外来、睡眠外来、訪問型の健康チェックサービスなど、「医療を核にした暮らしの提案」は多くの可能性を秘めています。
星は「院内にユニクロがある病院も出てきた。医療の場が地域住民にとって“立ち寄れる場所”になることが、次の時代のキーワードかもしれない」と語ります。
信頼性の高いブランドとしての病院。その価値をもっと柔軟に活用していく視点が、経営の持続性を高める一手となるでしょう。
健康づくり・予防・自由診療の可能性
医療費が増加する中で、病気になってから治すのではなく、病気を「未然に防ぐ」ことが社会的に求められています。
病院も例外ではなく、「予防医療」や「自由診療」をどう取り入れるかが今後のテーマです。
清水氏は、「病院が持つ信頼性を活かして、ダイエット指導、運動療法、栄養相談などのプログラムを展開できるはず。ライザップではなく、医療専門職による“安心できる予防支援”の価値が注目される時代」と語ります。
また、インバウンド需要への対応も視野に入れるべきです。
外国人観光客向けに、ホテルへの医師派遣や英語対応外来を行う病院も現れ始めており、高額でも「安心」を買いたい層は確実に存在します。
星は、「自由診療=金儲け」と捉えるのではなく、“保険外で地域住民の健康を支える手段”と見なすべきだとし、今後はそうしたサービスの企画力・発信力が重要になると語ります。
基本を丁寧にやることの重要性
医療経営が複雑化する今、奇抜なアイデアや新規事業ばかりが注目されがちです。
しかし、実際に赤字から脱却している病院の多くは、「基本の徹底」を疎かにしていません。
清水氏は、「特別なことはしていない。採用、教育、評価、ファイナンス、広報といった“当たり前”を丁寧にやっている病院が生き残っている」と語ります。
星も、「心理的安全性の高い職場づくり」「離職率の低減」「納得感のある人事評価制度」「適切なマネジメント体制」など、組織づくりの基本が経営改善の土台になると指摘します。
変化の激しい時代こそ、地に足のついたマネジメントが問われる。
これこそが今、あらゆる病院に求められている姿勢ではないでしょうか。
病院資源を活かした新規事業のヒント
最後に、病院が持つ「資源」を見直し、それを最大限に活かす視点が必要です。
建物、人材、信頼、ネットワーク、そして地域とのつながり。
これらを単なる「コスト」ではなく「資産」として捉えることが、未来への第一歩になります。
星は、「駐車場、病棟の一角、人材リソースなど、外部連携も含めて多様な活用法がある。医療資源を医療外にも広げることで、持続可能なモデルを構築できる」と語ります。
清水氏も、「医療者は職人気質で、ビジネス発想が苦手なことが多い。だからこそ、経営人材や外部パートナーとの協業が重要になる。医療の“信頼”という無形資産を最大限に生かす経営が、これからの病院には求められる」とまとめます。
※全文は編集された対談内容を基に構成されています。病院経営に関するご相談・ご質問はウェルタクトまでお気軽にお問合せください。